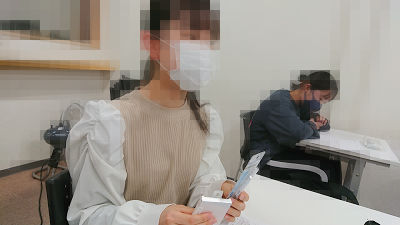一般言語学講義
2025年01月23日
受験には全く関係ない話です、興味のある方だけどうぞ。ソシュールの一般言語学講義の話です。
/////////////////////////////////
ある高校生から質問を受けました。
「思考するときのプロセスってどうしていますか?」
うーん難しいところを突いてきます。
「俺は文章を読んで、文節を一つ一つイメージ化して、それを矢印で繋いだりくみ上げたりしていくかなぁ(発達心理学とかチンパンジーの言語獲得実験みたいなことかな?)」
「いや、そう言う事じゃなくて、なんて言うんですかねぇ、僕の場合は考える時に頭の中で文字化して文字を使ってものを考えるんですが、人によっては違うんですかねぇ」
「文字を使わずイメージとかで思考するってこと?」
「そうです、多分」
「そういうことなら、世の中の人全てが文字を使って言葉で思考するよ」
「みんなそうなんですか?」
「多分、そう。文字がない限り思考はできない。」
「そう・・・なんですね・・・」
と。これ、まずは「言語学」という分野になってきます。
高校で倫理とか哲学みたいなことをやると出てくるのですが、「ソシュール」という人が言語学の祖とされており、「一般言語学講義」という本が出ています。
非常に難解な本ですが、簡単に言えばこうです。
普通われわれは、ものに名前をつけていると考えています。
つくえがあり、それに「つくえ」と名前をつけて呼んでいると思いがちです。(この考えがなぜ間違っているといえるのかは後述します)
ところがソシュールはそう考えませんでした。
「つくえ」という名前があり、その概念(すなわち「つくえ」という言葉が指すもののイメージ)に当てはまるものを「つくえ」と呼んで他のものと区別している
というものです。
たとえば、つくえというものがないアマゾンの奥地の人につくえを見せても、「変わった形の切り株」と思うかもしれません。それはその文化に「つくえ」=「ものを乗せたり勉強したりする台をつくえと呼ぶ」という考え方が存在しないからです。彼らには切り株とつくえを分けて考えるルールが存在せず、つまりつくえというものが存在しないことになります。
一方、我々は切り株とつくえを間違えません。切り株はこういうもの、つくえはこういうものというルールを文化的に持っているからです。切り株とつくえを言葉(すなわち文化)によって「分類」することで切り株とつくえを生み出している、というわけです。
さて、最初に出てきた「つくえにつくえと名付けている」というのがなぜ間違っているのか?ですが、もし「つくえ」というものに自動的に「つくえ」という名前がつけられるとしたら、世界中どんな言語でも「つくえ」というものには「つくえ」という名前が自動的に割り振られるはずです。ところがつくえは、日本語で「つくえ」、英語で「desk」ドイツ語で「schreibtisch」と表記します。全然違いますね。同じ物でも、それにあてがわれる言葉は言語によって異なってくる。ということは、物に自動的に名前がつけられるわけじゃないということになります。
一般言語学講義は難しい(あと本が高い!)ので、入門書を読んでみると良いと思います。
哲学や社会学などの人文系の学問一般に言えることですが、いきなり原典を(たとえ日本語訳だとしても)読むのは非常にハードルが高いので、まずはその解説書を読むと良いです。
これは、上記の高い本の訳者も共著している、その筋の専門家による入門書です。