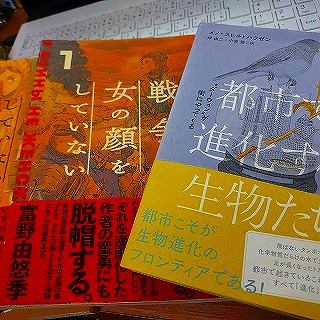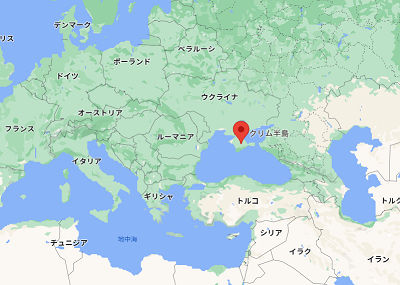子どもが怒られて帰ってきたとき
2025年07月21日
3年くらい前に投稿した内容を加筆修正して再度アップします。
直近で大きく怒るようなことがなかった今のうちに。
怒った時にアップすると「うちのことだ!」ってなっちゃうので。もし「これ、ウチのことかも・・・」と思われても、決してそうではありませんのでご安心ください。一般論です。
/////////////////////////////////
気をつけていただきたいのは、子どもと同化(親も一緒になって怒られたと思ってしまうこと)しないようにする事です。
お子さんが怒られて帰ってくるときにはそれなりに理由があります。そしてほとんどの場合、怒る側は改善を望んで、いくつもある選択肢から怒るという手段を選びます。(いつも怒っているだけとか、男子だけ、女子だけ怒るとかそう言う人は別です。あと、普段全く怒らない人も除いてください。偏っています)
そんなときはぜひ、怒られたのはなぜなのかを自分で考えさせる成長の機会と捉えてください。少なくとも開智塾ではそう捉えていただいて構いません。常日頃から講師間ミーティングでいろいろな子の報告をしあって、誉めようとか怒ろうとか諭そうとか、またはそれを誰がやった方がいいのか、保護者さんに電話入れておくべきかなどを考えて行動しています。つまり、「イライラして八つ当たりした」とか、そう言うことはありません。なにか理由や経緯があって怒られたということです。
でも、ごく稀に、お子さんがが怒られたときに自分が怒られたような気になって感情的になってしまう保護者さんがいらっしゃいます。これって子どもが自分の一部になっていて、自分まで怒られている気になってしまう、ちょっと共依存に近い現象です。悪い言葉を使えば、ちょっとした支配関係です。
言うまでもなく、子どもは自分ではなく他人です。別個の1人の人間です。子どもが怒られたのは、親が知らない別の場や社会において怒られる理由があったわけで、それは親とは関係ありません。大切なことなので2回言います。子どもが怒られてくるのは、親自身とは関係ありません。
気持ちは分かるんですよ、小さいときからずっと我が子を見てきて、今も目の前に「小さいときの延長の我が子がいる」のですから。ちょっとたとえはアレですけど、ずっと組み立ててきたレゴみたいな感じとでも言えばいいんでしょうか。
でも実際には、子どもは学校に行くようになって急速に「親の知らない世界」を身にまとっていきます。親の知らないレゴブロックがどんどんくっついていくわけです。核心部分は親が用意したものであったとしても、良くも悪くも他の要素がどんどんくっついてきて、子どもの世界は広がっていき、自分で動かす部分も増えていきます。そういうもんですよね。
そうなってくると、徐々に子どもは自分が怒られた事を自分で理解し、自分で直していかなければなりません。親は自分も一緒になって怒られた気分になっている場合ではありません。治すべきところを子どもが自分で直すのを手助けするのが親の役目になります。もしそれがお子さんにとって理不尽だと思えることであったとしても、です。理不尽なら理不尽で、「自分としては理不尽だと思います、なぜなら・・・」と、自分で言わせるようにすべきです。それもとても良い機会です。といっても、それはそう簡単な話ではないので開智塾の場合は事前に連絡をいただいて口裏を合わせておけるとスムースに事が進みます。こちらから声をかけるとか、ですね。
さて、開智塾で怒られた場合はどうしていただけるといいのかを書いておきます。そういう機会が減っている昨今ではありますけども。他で通用するかどうかは分かりませんがそんなに間違っていないと思います。
まずは子どもの話を冷静に聞く。まぁこれは当然ですよね。で、このとき子どもの話は7掛け5掛けくらいで聞いておきましょう。子どもは通常自分に都合良くしゃべるものです。自己防衛本能だからそれで当たり前です。だから親は冷静でなくてはいけないのです。
例えば自習室でしゃべっていて怒られたとしましょう。まずそもそも子どもは怒られたことは言わないものですが、(塾からの電話などで)バレたときには「しゃべっていて怒られた、でも私は話しかけられただけだ」とか言います(あとあと話を聞くと、なぜか全員が「話しかけられた側」ってのはよくある話です笑)。そんなもんですよね、子どもって。しかし学校でも塾でもきっと同じですが、怒る側からしたら誰が話しかけたか、話しかけられたかなんてどうでもいいんです。怒られる子は、はっきり言ってしまえば普段から目立ってます。何度も過去に注意されているが、その時はたまたま話しかけられた側だったかもしれませんが、子どもから親への報告は「何度も過去に注意されているが、実際その時はたまたま」の部分は省略され、「話しかけれた側だった」の部分だけを報告します。そんなもんです。子どもからすれば嘘はついていない(ホントも言ってないけど)からよく使われる手段です。そういう前提で話を聞かなければ、「良き理解者」ではなくただの「チョロい親」になってしまいます。
そうしてよくよく様子を探った上で、それでもあくまでも中立でいてください。自分の子どもが悪い比率が3:7なのか7:3なのか、そんなことはどっちでもいいんです。交通事故じゃないんですから。そして自分の何が悪かったか気づいていない場合は気づくよう考えさせる(一緒になって怒るともまたちょっと違います)。それで「良い経験になった」と思えるならそれでOK。また親も、親の立場として怒る必要があれば怒る。一方、「あれ?ちょっと状況がよくわからんな?」とおもうことがあるなら、お子さんに内緒で塾に内容の確認をする。そこで初めて「え?うちの子そんなに追試になってるんですか!?」みたいに真実が明らかになる場合も結構あります。もちろんこちらの誤解があることもあります。その時は素直にお詫びしています。「お詫びすりゃいいってもんじゃないでしょ!傷ついたうちの子をどうしてくれんの!!責任取って!!」そのフォローは・・・はっきり言いますけど親の役目ですよね・・・。それこそ一個の人格として、我々も本人にお詫びしますけども。こうみえて、ちゃんと生徒さん本人にも間違えたり言い過ぎたときはちゃんと謝ります。他の生徒の前で起こったことであれば他の生徒の前でちゃんと謝ってます。が、すみませんがそれ以上はどうしようもありません。それを恐れて萎縮し、結果何も出来なくなっているのが今の学校だったりするので。開智塾では「それでもなお、萎縮せず。言うべき時と判断したら言う」という方針を貫きます。
自分の子どもが他人に怒られる機会って、今の世の中極端に減っていると思いませんか?
近所のおばちゃんはおろか、学校ですらまず怒られません。中学生の宿題は0ですしね。「宿題忘れて怒られる」ことが、そもそも不可能になっちゃってます。でも開智塾はお預かりしているお子さんを自分の子どものつもりで見ています。怒った方がいいときは怒ります。大切なのはその後です。ぜひ、その後のために一緒に作戦を立てましょう。親が怒っているときは塾は引くとか、塾で怒られたときは家では静観しておくとか、色んな手が使えます。
そうそう、あと最近多いのは「うちの子、誉められると頑張るタイプなので」というのですが、それはみんなそうなんですよ。分かってます。怒られまくって伸びる子って今の時代にはまずいません。だから僕らも怒りまくることはしません。
しかし、だからこそ貴重な怒られた機会を大切にしてほしいのです。
怒られたあとは、大きく2パターンに分かれます。怒られたから次は改善できる子と、少しでも怒られたら即萎縮してそれっきり、です。そして厳しい事を申し上げますが、「怒られて萎縮する子」って、まず100%、保護者さんが「うちの子は怒られると萎縮する」って決めつけてしまっています。子どもは親が思っている行動をとるものです。子どもの行動を見て親が子どもを評価するのではなく、親の貼ったレッテルの通りに子どもは行動する。因果関係が逆なんです。これもまた子どもの姿です。分かりにくいのでちょっとたとえを出すと、「うちの子、体育が苦手なんです~」って言っちゃうと「そうなんです、私、体育苦手なんです」ってなります。「自他共に認める体育苦手っ子」に自ら進んでなってしまうというわけです。
もったいないですよね。子どもはどんどん成長して大人に近づいているのに親が子どもの性格を決めつけてしまうなんて。「怒られるなら自分に原因があるんやろ、自分でなんとかせんかい!不満があるなら自分で言ってこんかい!」でいいんですよ(実際の口調はお任せします)。
ちゃんと強さも身につけて欲しいですよね。なりたい自分があるなら、受かりたい学校があるなら、怒られたとかで止まってる場合じゃないはずです。良くないところを直してすぐ次に、ってならないと。上司に注意されたらいきなり退職するってんじゃ、社会人として困ってしまいます。マジでこういう話あるんですよ。あなたのお子さんも例外じゃありません。「退職代行?まぁ時代よね~。」といいつつ、「でも自分の子どもにはそうなってほしくない」というのが本音じゃないでしょうか。僕もそう思います。
一応補足しておきますと、「そんなこと塾ごときに求めてない」という意見もございますでしょう。もちろん、こういうことが不要であればやりません。塾は教育機関ではなく点数を上げるための産業ですから。ではなぜこんな塾からすればリスクしかないことをやるかというと、「点数を上げるために必要だから」です。それが分かっている程度には身の程をわきまえているつもりです。
しかし、時には自分の子どもを怒ってくれる人を信じてみてくださるとありがたいです。たぶん地球上にあなたのお子さんを怒ってくれる人は何人もいませんので。