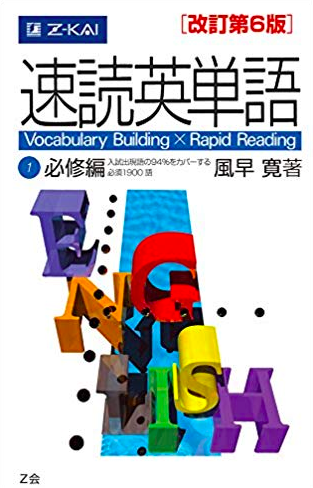国宝 感想
2025年09月30日
ちょうど話題になっていたのと、ご面談なんかでもお話がでて、これは見ておかねばということで見てきました。
がっつりネタバレです。もしこれからご覧になる方は、事前に「曽根崎心中」のストーリーだけは知っておいた方がいいと思います。
/////////////////////////////////
以下ネタバレ。

/////////////////////////////////
あくまで個人の感想です。分かりやすくするために、偏見に満ちたステレオタイプな「男性的」「女性的」という表現を敢えて使うことをお許しください。
/////////////////////////////////
まず全編通して見た感想は、「これは女性ウケするストーリーだなぁ」ということです。
理由は二つです。
①人間関係やストーリーが男子高校生部活ものに近い
②「血」という抗えない構造が女性の「ガラスの天井」構造に近い
①人間関係やストーリーが男子高校生部活ものに近い
「男性とはこうで、女性とはこう」と決めつけているのではありません。あくまで、よくある映画の作りとして、たとえば「社内の権力闘争」なんかはやっぱり男性ウケしやすい、といったような極めて単純化したストーリーで考えていくと、「女性的な映画だな」と思ったわけです。
この映画の「女性」性とは。
この映画は、見た目は男の物語ですが、中身はとても「男子高校生の部活もの」ぽい構造でできていると感じました。競い合うようでいて、そこには友情や信頼といった「受け入れる力」、相手の苦しみを理解しようとするやさしさが物語の根底に、当然のこととして流れている。
「男向け映画」では、多くの場合「勝つか負けるか」「結果を出すかどうか」で関係が決まる部分があり、ヤクザ映画なら負けた側が死んで終わるという単純明快な結末になったりします。それが最終的な「この映画面白かった!」に通じがちなんです(半沢直樹や北野武『アウトレイジ』シリーズなんかはやっぱり「男性ウケ」の世界だと思います)。ところが『国宝』の世界には、そういう直線的な価値観がビックリするくらいありません。
2人はライバルでもありながら、お互いに助け合い、支え合うという関係の中にあります。同じ部活に属してライバルとしてポジション争いをしながらも、やはり最終的な「強豪校に勝利する」という共通の目標に向かって支え合う友情に近いといってもいい。スラダン、ハイキュー!!とか。そういう点で、ある意味優れて「女性ウケする」関係にも思えるのです。
全編を通して、2人の関係はとても神々しい。あまりに神々しすぎて、なぜ2人が憎しみ恨み、妬み合う関係になりきれないのか、そこは僕にとって一つ大きな理解への壁となりました。
②「血」という抗えない構造が女性の「見えない天井」構造に近い
物語の中心にいるのは二人の男。
一人は「血」を受け継ぐ者=俊二郎(俊坊/横浜流星)、もう一人は「芸」を持つが「血」を持たない者=喜久雄(吉沢亮)。
前者は血によって縛られるが故の苦悩を背負い、後者は血を持たざることで、どれだけ芸を磨いてもどこかで見えない「血」に阻まれ続ける。
この構図は、2人のどちらを見てもどこか女性の生きづらさに近いような気がします。
「血」を持てばそれが大きな足かせとなり、持たなければやはりそれは障壁となる。
女性は現代においてもやはり生まれ持って「ガラスの天井」(マリリン・ローデン)に覆われている現実がある。血を巡って苦しむ2人の姿は、どちらを見ても男性より女性の方が実感しやすいのではないか(ここは想像に過ぎませんが)と思いました。
同様に、「努力と根性で乗り越えろ」という価値観を刷り込まれた男性社会を生きる者にとって体感的な理解が難しい部分に感じます。血脈を前提とした歌舞伎役者という特殊な世界そのものが、頭では理解していてもリアルな実感を伴って感じづらい部分です。
それぞれの運命の中で、2人の間にあるのは「受け継ぐ」「受け入れる」「赦す」「見届ける」という円循環の感情。この感情の流れは映画の「女性」性に直結している部分だと思いました。
やや蛇足的ですが、古来より少女マンガなんかでも「○○の生まれ」みたいな血脈系や御曹司系はテーマとして人気ですよね。
血脈ものだと古くは『王家の紋章』(細川智栄子・芙〜みん)、『CIPHER』(成田美名子)、『ベルサイユのばら』(池田理代子)など、近年だと『推しの子』(赤坂アカ×横槍メンゴ)なんかもこの系譜でしょうか。
御曹司ものだと『花より男子』(神尾葉子)『桜蘭高校ホスト部』(葉鳥ビスコ)
近年では『かぐや様は告らせたい』(赤坂アカ)(←2015年連載開始、なんと10年前!!)など、枚挙に暇がありません。
こういう観点でもやはりコレ系は女性に好まれがちなテーマかな、って思います。
/////////////////////////////////
作品の「色彩」の持つ力
この映画を見ていて特に印象的だったのは、血のような赤と、雪や照明の白。ただし艶やかな赤とは感じませんでした。血液の色、ちょっと生々しいまでの深い赤色。
この二つの色が交互に、あるいは同時に現れるたびに、感情が大きく揺さぶられました。
白は清め、赤は生の象徴。
その二色のコントラストが、「生まれ」「死」「伝承」「断絶」といったテーマを、説明するよりも先に、感情として理解させてくるんですよね。白が美しければ美しいほど、そこに滲む赤が際立つ。
その構図はまさに、芸と血、生と死、救いと呪いの対比そのもの。
論理ではなく視覚で、見るものの心を奪っていきます。
しかし、それでいて「生か死か」(dead or alive)という二項対立ではなく、それらが表裏一体となって循環するさまは、非常に東洋的な、輪廻の世界観に近いと思います。
日本人は(といっていいか分かりませんが)白と赤の対比を大切にします。どちらが好きと言うことではなく、多くの場合それらは連続して現れます。
紅白幕は古来より「ハレ(白)」と「ケ(赤)」であり、幕が結界であり、結界のうちにいるものの団結や結集の象徴でもありました。『国宝』においては、赤はおそらく血、生命。白は清め、死、再生。こうした宗教的価値観と色彩感覚は無縁ではないと思います。
(余談ですが、日本人がショートケーキを好むのも、この「白と赤の調和」を美と感じる文化の延長にあるのかもしれません。アメリカのケーキのような派手な色彩は、どこか異質に映るのです。)
/////////////////////////////////
血を持たない者が最後にたどり着いたのは、不純物を全部削ぎ落とした「芸そのもの」の世界。
最後の雪(だと思う)の舞う舞台のシーン。究極の美にたどりついた瞬間。「美しいものを美しいと感じ、表現できる瞬間」だけの、極めて混じりけのない、限りなく透明に近い真っ白な場所。
でもその景色は、かつて自分の父が雪の中で死んでいったときの雪景色とオーバーラップしているように感じました。
つまり結局彼は、ヤクザものの世界を離れて芸に生きる新たな人生を完成させた・・・のではなく、父と同じ人生を生き直したのではないか。すなわち、役者としての血を持たぬ者が、最後にヤクザものとしての血を再演する。ある意味それは喜久雄という人間としての芸の完成であり、同時に血の呪いの再生でもある。
ヤクザものという血から離れ、自由を得たように見えて、実は輪廻へと引き戻されていく。
これは悲劇かもしれませんが、僕は「至るべき所に至った幸福」のようにも思えました。
雪の舞台は、清めの白でもあり、墓標の白でもあります。その中で彼が舞う姿は、人間というより芸そのもの。血も欲もすべてを手放して、ただ美しさだけを残す。しかしその美しさが、彼の背負う業の全てを覆い隠すため、結局なにも解決はしていないのだけど。
けれど、あの白と赤の対比が作り出す美、そして最後全てを覆う白は圧倒的で、「それでもいい」と思わせてしまう。
それがこの映画の魅力の一つだと思いました。
/////////////////////////////////
おそらく『国宝』が描いたのは、「宿命を超える」話ではなく、「宿命を美として引き受ける」話ではないか。だからこそこの映画は、静かに観る者自身に「生の美しさ」を問いかけてくるのだと思います。
宿命から逃れようと、美しく生きる。しかし美しくあろうとすればするほど、逃れられない宿命の中心へと引き寄せられていく。
芸という呪いの中で、それでも光を見つける。それが、あの雪の舞台の意味だったのだと思います。
最初に感じた「女性ウケする」という印象も、その「美しく赦す構造」のせいかもしれません。
/////////////////////////////////
あと、どうしても最後に残ってしまうのが「おそらく原作(分厚い上下巻)の主要どころを削ぎにそぎ落としてこうなったんだろうな」という「ダイジェスト感」です。ここは仕方ないとか不満とかより、おそらく監督が相当苦労して、原作の筋立ての大切な部分を極限の努力で描ききったのだろうな、とおもいます。それがひしひしと感じられる(原作読んでないですけど)のも、また一つのすごさだったと思います。