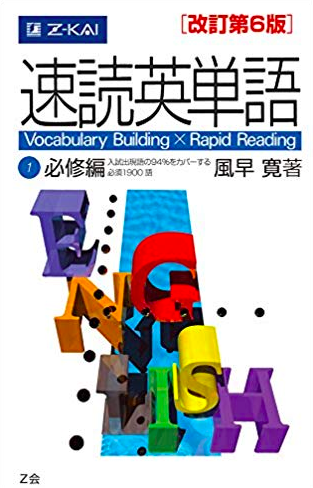現代もやもや考
2025年07月24日
どうでもいいっちゃどうでもいいんですが、勉強に通ずるところがあるかなという話です。
最近よく「モヤモヤする」「モヤっとする」という言葉、耳にしませんか?語感的には平仮名で「もやもや」の方がいいかな。
語源はおそらく「靄(もや)がかかる」でしょう。言葉自体は古くからあり、
「切々なるこころのもやもや、如何」(『名語記』1275年)(コトバンクより)
さらに、江戸期の浮世草子(という、日常や生活を題材にした小説)の「好色一代女」にも
「しどけなく帯とき掛けて、もやもやの風情見せければ」 (『好色一代女』)
と出てきますが、こちらは欲情するとかそっち系の意味で使われています。
さらに明治・大正期になると
「革の焦げる臭気と共にもやもや水蒸気を昇らせていた。」(芥川龍之介「寒さ」)
「・・・は自然の斥候のようにもやもやと飛び廻った。」(有島武郎「カインの末裔」)
など出てきますが、こちらは感情を表すのではなく文字通り「もやもやとした風景」を描写しています。
いずれにせよ「もやもや」は感情や情景を表す語として古くからあったようです。
さて時代は飛びまして、ごく最近「もやもや」が負の感情を表す語として頻繁に使われ出したのは、googleトレンドサーチによれば 、
(グラフは回数ではなく、最大を100とした相対値です。ごく初期の大きな山は外れたいな気がしますがどうでしょう)
「もやもやする」は2009年12月に検索ワードとして登場して、次に登場するのが2011年3月。それ以降はずっと検索され続けていることになります。
2009年は、「1Q84」「おくりびと」「マイケルジャクソン関連」の年です。
とりあえず「もやもやさまぁ~ず2」という番組が2007年に始まっています。この番組がきっかけ・・・というよりは、この頃にちょっとしたトレンドで「もやもやする」という言葉が出てきて、それに番組名が乗っかったというのが正しい気がします。
2011年3月に再登場しますが、東日本大震災(ちょうど2011年3月です)、原発関連、なでしこジャパンW杯優勝、流行語に「どや顔・絆・まるまるもりもり」の年でした。
一方「モヤる」(カタカナ)
2006年8月に多量に検索されているのですが、本当にすごく流行ったのか、何らかの外れ値なのか分かりません。※ただ、この頃すでに個人のブログなどで「モヤモヤする」的な表現が多く見られるので、既に「モヤる」の芽が出ていた可能性はあります。
(※外れ値というかデータのエラーだったようです)
その後、継続的に検索されるようになるのは2016年10月ころからです。
2016年は、ボブ・ディランのノーベル文学賞、津久井やまゆり園事件、「保育園落ちた日本死ね」、ポケGOの年です。
この「モヤる」は、2018年に、三省堂の「今年の新語」2位になっています。
「もやもやする」から遅れること約7年。言葉が簡略化、動詞化するのにかかる期間としてはちょっと長い気もします。
(ちなみにひらがなで「もやる」にすると、多分「野球もやる」みたいなのが引っかかってくるのでは?というグラフになっています。真相は不明ですが。)
/////////////////////////////////
「もやもやする」という言葉、
・不快感を、
・直接的には表現しない
非常に日本人的で、使い勝手の良い言葉だと思います。
特に2011年3月以降に検索ワードとして広まったとすると、震災の影響は無視できない気がします。「悲しまなければならない」「楽しいことは不謹慎である」という一種の同調圧力(確かに当時はACの広告ばかりになりましたね)が強く、心の内の負の感情を明確にするのは憚られる社会情勢だったと思います。まさに「もやもや」がちょうど良い表現だったといえるのではないでしょうか。
ところで、「モヤモヤする」というお気持ち表明は、使いようによってはとても強い攻撃となることがあるように思います。
ドラマで聞いたセリフ(確かこんな感じ)ですが、
「あ、別に謝って欲しいとかそんなんじゃ無くて、ちょっとモヤッとしただけです。別に謝らなくていいです。〇〇さんが悪いって言いたいわけじゃありませんから」
結構言われるとイヤじゃないですか?
これがイヤな理由をかんがえて見ました。
ストレートに怒りをぶつけることなく「モヤッと」だけにしておけば、
・自分を安全圏に起きつつ、
・その解釈を相手に丸投げし、
・言葉が曖昧だから何がどう不快かを漠然とぶつけることができる
からじゃないでしょうか。
本来なら「あなたの〇〇という言い方は、△△という理由で傷ついたからやめてほしい」と伝えるべきところを、「なんかモヤッとする」みたいな感じで強烈な不快感をぶつけて終わらせるわけです。
明らかな抗議なんですが、表向き抗議の体を取ってはいないので、言われた側は謝ることも出来ません。なにせ「謝ってもらわなくていいんで」って言われちゃってますし。
となると、爆弾をくらった側にそもそも「モヤっとさせるつもりがない」場合はとても大変な事になります。なにせ、何がどう不快だったか分からないので、
「傷つけた?」
「迷惑をかけてしまった?」
「なにがいけなかったんだろう?」
と、自分の非の範囲を無限に拡大させてあれこれ考えなければなりません。でも、たいていこういう場合「なにに、どう、モヤッとしたか」は教えてもらえません。なにしろ、それをはっきりさせないための言葉ですから。
こうなってしまうと、何について謝るべきなのかとか、何を改善すべきなのかが分からないだけでなく、「そんなつもりはなく、こういうことが言いたかったのだ」といった弁明の機会すら与えられない状況に陥るわけです。
「最近の賃金上昇のニュース、物価が上がってること考えるとなんだかモヤッとするわねぇ」など、一般論や漠然と使うならいいと思うんですが、相手が目の前にいて不快だったなら、それはやっぱりきちんと伝えた方がいいのでは?と思います。
/////////////////////////////////
とまぁ、それはともかく。受験を考えると、「なんとなく」の感情を「モヤッと」みたいな言葉で終わらせてしまうのではなく、明確に伝える練習をした方がいいなぁと思うわけです。さすがに回答欄に「モヤッとした様子」とか書けないですからね。
「モヤモヤ」に限らず、「ヤバイ」「エグい」だけでプラスもマイナスも全てカバー出来てしまうのは、それはそれで面白い現象ですし言葉というものはそういうもの(時代とともに単純化されていく)だと思うのですが、それだけでは少なくとも受験の国語では苦労するぞ、と思ったりします。